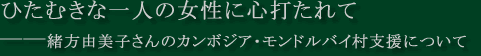アンコールワットの遺跡を横に見ながら走っていると、ボロボロの服をきた裸足の子どもたちが賑やかに付いてきます。
それは12年前のこと。カンボジアには多くの地雷が埋まっており、日々子どもたちが被害にあっていました。戦闘力を奪う目的で作られた対人地雷は、命こそ残ったとしても、生活に大切な手足を奪ってしまう恐ろしいもの。その被害に苦しむ姿を、一人の日本人女性が目の当たりにしたところから、一つの支援活動が始まったのです。
 当時、緒方由美子さんは国連支援交流財団の広報部長を担っていました。アンコールワットの回りに埋められた無数の対人地雷は、NGOを初めとした世界各国の有志により撤去作業が進められていました。そんなとき「アンコールワット周辺で国際規格のハーフマラソンをしたい」との声が上がったのです。
当時、緒方由美子さんは国連支援交流財団の広報部長を担っていました。アンコールワットの回りに埋められた無数の対人地雷は、NGOを初めとした世界各国の有志により撤去作業が進められていました。そんなとき「アンコールワット周辺で国際規格のハーフマラソンをしたい」との声が上がったのです。
そこにはカンボジアはすでに平和を取り戻し、アンコールワットの周りは安全なのだとアピールする目的と、マラソンのエントリーフィーを、子供たちの義足を作る費用に当てたいという思いがありました。大阪女子国際マラソンを企画運営してきたサンケイスポーツの結城氏が発案したハーフマラソンは、オリンピックメダリストの有森裕子さんの賛同も得、準備が進められていたある日、私の家の電話が鳴ったのです。「竹岡さん、知恵を貸して欲しい」
緒方さんと会い、話を伺った私は彼女のひたむきさに打たれ、「なんでもやりましょう」、と即答しました。早速NTTドコモ、明太子のかねふくへスポンサーになっていただけるよう申し入れ、快く引き受けていただいたところから、私のカンボジアへの応援はスタートを切ったと言えます。
 当時私は、聖教新聞社に勤務しておりました。第1回のアンコールワット国際ハーフマラソン開催時に、初めてカンボジアを訪れました。職場には、「人間ドックを受診する」と有給休暇を取っていたのですが、カンボジアで走っている私の姿がテレビに映ってしまい、騒ぎになったのが今では懐かしい想い出です。
当時私は、聖教新聞社に勤務しておりました。第1回のアンコールワット国際ハーフマラソン開催時に、初めてカンボジアを訪れました。職場には、「人間ドックを受診する」と有給休暇を取っていたのですが、カンボジアで走っている私の姿がテレビに映ってしまい、騒ぎになったのが今では懐かしい想い出です。
緒方さんと私は、小学生、中学生、高校生に参加、エントリーしてもらおうと必死に呼びかけを行いました。しかし、なかなかエントリー者は集まりません。なぜならば「意味もなく走る」習慣が、彼らにはなかったからです。彼らにとって「走る」とは、敵から追いかけられたときに命を守るため行う行為でしかない。それを初めて知った私は、言葉を失くすほどショックを受けました。そして、まずは走ることから教えることにしました。次に、沿道で、笑顔と拍手で応援してもらおうと企画をしました。しかし、これも難しいことがすぐにわかりました。それは、彼らは笑顔から遠ざかった生活を強いられていたのです。
 命を守るために、命を奪われないために逃げている人を、なんで笑顔と拍手で迎えるのか、という彼らの素直な疑問を聞いた時には、地に落とされたような精神的なギャップを感じました。私、自らが手をたたきながら、笑った顔を見せて、走ることや応援することを教えました。それは、それは、とても難しいことでした。自分にとっても、初めて味わうショックそのものでした。そして、もっとショックだったのは、正規にゼッケンをもらった子どもは、まだ良かったのです。裸足で、ボロボロの服を着て、着いてくる子どもたちがいたのです。どこの子どもたちだろう、と調べると、全く戸籍を持たない子どもたちだったことがわかりました。
命を守るために、命を奪われないために逃げている人を、なんで笑顔と拍手で迎えるのか、という彼らの素直な疑問を聞いた時には、地に落とされたような精神的なギャップを感じました。私、自らが手をたたきながら、笑った顔を見せて、走ることや応援することを教えました。それは、それは、とても難しいことでした。自分にとっても、初めて味わうショックそのものでした。そして、もっとショックだったのは、正規にゼッケンをもらった子どもは、まだ良かったのです。裸足で、ボロボロの服を着て、着いてくる子どもたちがいたのです。どこの子どもたちだろう、と調べると、全く戸籍を持たない子どもたちだったことがわかりました。
 その後、緒方さんたちの努力が実って、たしか3回目には、現在のフンセン首相も参加する行事に発展しました。そしてあるとき、その人道支援をする緒方さんの姿をみて、シェムリアップ州の知事が緒方さんにどうしても見てもらいたい、そしてもっと支援してもらいたいところがある、といって、ある村に連れて行ったのです。そこが、非合法で、地雷の被害がいっぱいの障害者の村、モンドルバイ村でした。そのモンドルバイ村の悲惨なありさまを目の当たりにしたとき、緒方さんはアンコールワット国際ハーフマラソンの運営支援は、有森さんが代表をしているNPOハート・オブ・ゴールド法人(1998年の設立)に主体をまかせ、このモンドルバイ村の支援に、心も、からだも、時間も、お金も、自分の全てをかけていく、一人のひたむきな女性の姿になっていったのです。緒方さんが、このモンドルバイ村でやった素晴らしいことは、まず、戸籍調べをやったことです。草むらの中に、もちろん電気も、水道も、何もない。ただ掘っ立て小屋があるだけ。そんな中に約600世帯、3000人が住んでいたのです。
その後、緒方さんたちの努力が実って、たしか3回目には、現在のフンセン首相も参加する行事に発展しました。そしてあるとき、その人道支援をする緒方さんの姿をみて、シェムリアップ州の知事が緒方さんにどうしても見てもらいたい、そしてもっと支援してもらいたいところがある、といって、ある村に連れて行ったのです。そこが、非合法で、地雷の被害がいっぱいの障害者の村、モンドルバイ村でした。そのモンドルバイ村の悲惨なありさまを目の当たりにしたとき、緒方さんはアンコールワット国際ハーフマラソンの運営支援は、有森さんが代表をしているNPOハート・オブ・ゴールド法人(1998年の設立)に主体をまかせ、このモンドルバイ村の支援に、心も、からだも、時間も、お金も、自分の全てをかけていく、一人のひたむきな女性の姿になっていったのです。緒方さんが、このモンドルバイ村でやった素晴らしいことは、まず、戸籍調べをやったことです。草むらの中に、もちろん電気も、水道も、何もない。ただ掘っ立て小屋があるだけ。そんな中に約600世帯、3000人が住んでいたのです。
 そして、次に手がけたことが、小学校の建設です。当時の子どもたちは、アンコールワットに来た外国人観光客に、うちわであおいだり、楽器を演奏したり、観光ガイドをやったり、手足がなくなった子どもを見せて物乞いをやって、なんとか生計をたてていました。そこで稼ぐ1日1ドルのチップで、一家5人が1週間暮らすことができました。しかし、緒方さんは、これから彼らが自立していくためには、ちゃんと教育をしないといけないということを、ひしひしと感じていました。そこで、『希望小学校』の建設に着手したんです。さらに子どもが大きくなるにつれて中学校の必要性が出てきて、中学校の建設を目指します。
そして、次に手がけたことが、小学校の建設です。当時の子どもたちは、アンコールワットに来た外国人観光客に、うちわであおいだり、楽器を演奏したり、観光ガイドをやったり、手足がなくなった子どもを見せて物乞いをやって、なんとか生計をたてていました。そこで稼ぐ1日1ドルのチップで、一家5人が1週間暮らすことができました。しかし、緒方さんは、これから彼らが自立していくためには、ちゃんと教育をしないといけないということを、ひしひしと感じていました。そこで、『希望小学校』の建設に着手したんです。さらに子どもが大きくなるにつれて中学校の必要性が出てきて、中学校の建設を目指します。
そんなさなか、親を亡くした子どもたちなどの孤児院の支援に問題が起きます。それは、フランスがアンコールワットを管理することになり、子どもたちが中に入れなくなったのです。それは、彼らの生活の糧が無くなるということです。子どもたちがやっていた、うちわであおいだり、観光ガイドをやったりのアルバイトの道が閉ざされるということだったからです。元々、非合法の村だから。モンドルバイ村が観光地のアンコールワットに近いからということで、政府から立ち退き命令が出たのです。緒方さんは、政府の高官に、なんども何度も、掛け合いました。そしてついに、モンドルバイ村が、そのまま立ち行けるように阻止したのです。
このモンドルバイ村は非常に衛生管理が悪いところです。すごい蚊が発生します。そして蚊はマラリアを運びます。また、雨期には冷え込む夜が続きますが、からだを温める毛布すらなかったのです。緒方さんは、そこで暮らす人たちの健康のために、1軒に1つのカヤと、一人に1つの毛布を送る運動を展開しました。また、日本からの届く多くの支援物資が途中でピンハネされるという現実にも悩まされました。そのため、緒方さんは自分で、物資1個1個を確認したり、現地で調達するように切り替えたりと、涙ぐましい努力を始めたのです。
さらに孤児院の子どもたちの自立のために、彼女はクメールダンスを復活させました。ポルポトとの内乱の時代には、文化、教育活動は禁止、中止され、文化・経済の荒廃が進んでいました。そして、伝統文化の継承をする人も多くの命を失っていました。そんな中、長老から教えてもらい、習い、ダンスを踊れるまでにしたのです。そして、ホテルで披露するまでになりました。その孤児院の子どもたちが今年、来日しました。法政大学のボランティアメンバーと一緒に、このクメールダンスを日本で披露したのです。日本でこのダンスを観たとき、たった一人の女性の叫びが、ここまで実を結ぶまでになったのかと感慨に堪えない思いで、目頭が熱くなりました。

今後も出来る限りの支援を、私も一緒にしていきたい、と思っています。幸い、緒方さんの情熱と努力は多くの方々に広がりを見せ始めています。2008年2月には新日本製薬株式会社の若き36歳の経営者、後藤孝洋社長が来村し、そして来年は彼の友人の前田嘉秋社長という更に若い経営者も、モンドルバイ村を訪れる予定になっています。後藤社長は自社のサプリメントを老人会に差し上げ、膝が痛い人に喜ばれています。また、一貫して変わらず支援を続けてくださっている、かねふくの竹内昌之社長には、心から感謝申し上げます。
今年、モンドルバイ村に行ってわかったのですが、電気が来ていないから、当然、冷蔵庫もないんですよね。だから、川から捕る魚も、その日の分しか捕らない。当然、市場でもその日の分しか売っていないんです。電気がなくて、夜は早く寝て夫婦円満で子どもも多い。今年、井戸を掘るのを手伝って来ました。生きるに足る、水を確保する、そして食べ物を確保する。人間として教えられることがいっぱいありました。小欲知足とはこのことか、日本も、もう一度このことを学び直してもいいのではないか、などと考えさせられたりもしました。
手足を奪う非人道的な地雷、この地雷に、今も、今年も悩まされています。それは、カンボジアでは洪水が頻繁におきるからです。この洪水のたびに、新しい地雷が上流の山岳地帯から流れ出てくるんです。そのため、毎年、人の被害が耐えません。この支援の活動は、遙かな虹の晴れやを望むに等しいものかもしれません。しかし、一人の女性のひたむきさが、一歩一歩と歩みを進め、輪を広げ、晴れやに近づいていることは実感できます。
私は将来、この『希望小学校』からカンボジアをになって立つ、また世界で活躍する人材が出て来ることを確信しています。また、オリンピックのマラソンでメダリストが出ることを夢見ています。緒方さんは、『希望小学校の校歌』(パンフレット既掲載を参照)を作って教えています。そして、その校歌をみんなが歌っています。私は彼女の文化レベルの高さを感じます。物資や建設といった支援だけではない。人間が生きていく上で基本となる文化、そして悲惨な時代に失われた文化を、あらためて育てる運動。とても素晴らしい活動だと、心の底から拍手を贈りたい。
 この支援活動を、緒方さん自身は恩返しだと思って取り組んでいます。それはご自分のお子様がひ弱だったために多くの人に面倒を見てもらった、だからここまで打ち込めるのかもしれません。そう語っていた言葉は、人として報恩、感謝ということが、いかに人間を突き動かす原点になるのか、そして大切なことであるのか、と思いをあらたにしています。
この支援活動を、緒方さん自身は恩返しだと思って取り組んでいます。それはご自分のお子様がひ弱だったために多くの人に面倒を見てもらった、だからここまで打ち込めるのかもしれません。そう語っていた言葉は、人として報恩、感謝ということが、いかに人間を突き動かす原点になるのか、そして大切なことであるのか、と思いをあらたにしています。
最後に、第1回のマラソンを飛び入りで走ったハダシの男の子「ロン」という子がいました。アンコールワットの中で私の側によってきて、おしつけで旅先案内をしてくれた子どもでした。5歳でした。友達になって以来、毎年いっしょにハーフマラソンを走っていました。そのロンが6年前に亡くなりました。実家とお墓(といっても家の側に埋めただけ)にお参りにいっていたのですが、今年訪ねたとき、妹が「ロン」はアンコールワットの中に葬られました。と、私に告げました。アンコールワットは私にとって、また、特別の存在になりました。
![]()